12年にわたって介護してきた母が亡くなり、はや一年になります。母を無事に見送ったことで、「次はとうとう自分だな」「自分の人生をどう終えたいかな?」という意識も芽生えたころ、この仏映画に出会いました。
今回は、この映画に何度か登場し、私の心に残ったセリフをご紹介します。
『すべてうまくいきますように』TOUT S’EST BIEN PASSE
EVERYTHING WENT FINE (2021)
キノフィルムズ
作品の概要については、allcinemaから引用します。
「8人の女たち」「Summer of 85」の名匠フランソワ・オゾン監督が、安楽死を決断した父と、戸惑いながらもわがままな父の最後の願いを叶えてあげようと協力していく家族の葛藤と絆をユーモアを織り交ぜ描いたヒューマン・ドラマ。出演はアンドレ・デュソリエ、ソフィー・マルソー、ジェラルディーヌ・ペラス、シャーロット・ランプリング。
人生を謳歌してきた85歳のアンドレが脳卒中で倒れ、命は取り留めたものの、身体の自由がきかなくなってしまう。その現実を受け入れられず、彼は安楽死を決断する。娘のエマニュエルは父から協力を求められ困惑する。しかし頑固な父の性格を知る彼女は妹にも相談し、躊躇いながらもスイスの尊厳死協会に連絡を取ることに。そんな中、リハビリが功を奏し日に日に回復していくアンドレだったが…。
「人生は美しい(La vie est belle.)」

この映画のなかで何度も繰り返し現れるセリフ。
「人生は美しい(La vie est belle.)」
父親のアンドレが、弁護士から指示され自殺の意思を録画する際に語るセリフであったり、父親をスイスの尊厳死協会まで送っていく救急車の運転手の若者が口にするセリフであったり。
限りある人生。
いずれ死んですべて失われるからこそ、それがわかっているからこそ、命が輝き、一瞬一瞬が愛おしく感じられる。そして、胸に刻まれた記憶や思い出が、二度と戻らないからこそ、かけがえのないものとなる。それこそが美しい人生といえるのかもしれません。
生きていると日々、悩んだり、怒ったり、悲しんだり、苦しんだりと負の感情のほうに振り回されている気がします。でも、近頃はそんなネガティブな感情すら大切なものに感じられてきました。
いずれは感情の起伏もなくなってしまう、喜びも悲しみも薄れていってしまう、心の動きすら、消えていってしまう。
若い頃には想像もできなかったことですが、私の母がまさにそうでした。
もちろん、それは悪いことばかりではありません。穏やかな気持ちで日々を生きられるなら、それが老いの幸せというものなのかもしれません。
とはいえ、私自身、今しばらくはやはりとことん泣いたり笑ったり、悔しい思いをしたりしたい、それでいい、人間なのだから、と感じています。
旅の愉悦

母の最後の旅、鳥取旅行でのことでした。亡くなる数週間前のこと。
それまで母の世話をあれこれ焼きすぎて本人のリハビリにならないと反省した私は、母自身ができることはなるべく本人に任せようとしました。すると母も自分でペットボトルの水を飲んだりするなど可能な範囲で応えてくれました。
当時の母は感情の起伏がほぼなく、何をたずねても「わからない」と答えることが多かったのです。デイサービスから帰ってきて一日の出来事をたずねても、ほとんど何も覚えていませんでした……。
そんな調子ですから、あまり会話らしい会話が成り立たなくなっていましたね。
ところが久しぶりに旅に出て大いに刺激を受けたせいか、鳥取旅行中はホテルの窓から朝日を眺めて「きれいやなぁ」と何度もつぶやいたり、地元の瓶入りコーヒー牛乳を飲んで「おいしい、おいしい」と感想を言ったりしたのです。
一番うれしかったのは、昔の母に戻ったかのような瞬間があったことです。他人のマナー違反に対して、母が怒りをあらわにしたのです。
トイレ近くの場所で母に車椅子のまま待ってもらっていたのですが、どうやら若い女の子が濡れた手を振りながらトイレから出てきて、母に水滴がかかったみたいでした。そうしたら母が「やらしいわ、水がかかったやないの~」とぷんぷんしながら文句を言ったんです(笑)。
たいした話ではないのですが、いつもぼんやりとしていた母がまるで昔に戻ったかのように喜んだり、感動したり、腹を立てたりしたので、娘の私は驚きつつ、心からうれしいと思ったのです。本来なら「うるさいなぁ、そんな細かいことで愚痴らんでもええやん~」と思うところではあるのですが。
母との最後の旅行は、いま思い返せば、まるで奇跡のようでしたね。
さいごに

本題に戻りましょう。
この映画で父親が安楽死を望む理由について。
やはり体の自由がきかなくなったからだ、と最初は思っていたのですが、どうやらそうともいえないようです。実際、リハビリが功を奏して回復している描写がありました。結局、理由ははっきりと描かれていないように感じました。
監督が描きたかったのは、自分の意思で最期を決めるということかもしれません。そして家族がその意思を受け入れ、尊重し、安楽死の手伝いをする、その悲喜こもごも。
芸術と美食を愛するゲイだった父親(元カレとのいざこざもあり!)。でもちょっぴり悲しいと同時にくすっと笑いを誘うことに、「孫の演奏会を見ずに死ねん」と息巻いていたはずが、当日は途中でこくりこくりと居眠りしていたり。
救急車(おそらく民間の救急車?)でベルンへ行く途中、安楽死の件がばれて、若い運転手から「なぜ死のうと? 人生は美しい」とたずねられても、父親は苦笑して黙りこんでしまいます。
たぶんわかってもらえるはずもない。未来ある若者と人生の終わりを迎えた老人とでは、どうしても伝わらない心境があるのでしょう。私自身、父親の心情に近い気持ちもありますから。
父親は運転手たちに告げます。「私が決断する。娘たちではない」
最後まで自分の意志を貫けることこそ、美しい人生、すばらしい人生なのかもしれません。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!
みなさま、どうぞ、なるべくなら悔いのない人生を
送ってくださいね




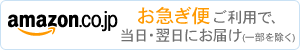

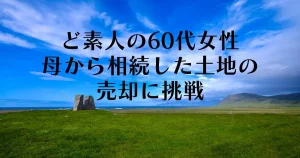





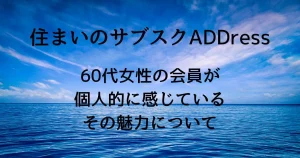
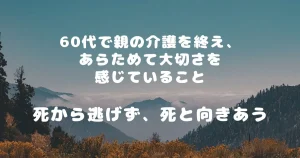
コメント