村上春樹という作家。20代のころから断続的に読みつづけてきた。正直なところ、60代になった現在、彼の長編はどちらかといえば苦手なのだが(ごめんなさい!)、短編にはときとしてぐっと胸をつかまれるような思いがするときがある。
胸の奥に眠っていた何かがふと揺さぶられ、不意に目覚めるような、胸が苦しいような……とにかく心の奥底に訴えかけてくるものがあるようだ。
それは爽快なものとはほど遠くて、なんともいえない底の知れない不安感や孤独感といったものかもしれない。
今回はある短編にガツンとやられてしまったので、20代からの私の短編遍歴を振り返りつつ、その忘備録として書きとめておきたくなった。
※本編から一部抜粋しています。未読の方はご注意ください。
20代~40代 心魅かれた短編たち「午後の最後の芝生」「中国行きのスローボート」「トニー滝谷」

短大生だったころに「午後の最後の芝生」という短編にみょうに心魅かれた。
短大の卒業時だったかなにかの折に下手くそな英訳をして先生に提出したことを覚えている。手書きの絵の表紙までつけて……。いま思い返せばかなり恥ずかしい。でもそれほどまでにこの作品に魅了されていたのだろう。
次に思い出すのは「中国行きのスローボート」。
どんな内容だったかすらよく覚えていないけれど、作品中で何度か繰り返される「誤謬(ごびゅう)」という言葉がやけに頭に残っている。当時この言葉を初めて知ったということもあるけれど……。
私は全作品を読破しているわけではないし、むろんハルキストを自称するような熱狂的ファンでもない。長編はむしろ苦手だし、大ヒットした『ノルウェイの森』はぜんぜんぴんとこなかった。
村上春樹の恋愛ものはどちらかといえば苦手。性的な描写もちょっと受けつけなくて。いやまぁ、恋愛ものは小説にしろ映画にしろ概して苦手なのだけれど。
そして中年以降に出会ったのが、映画版を見てから原作を読んだ「トニー滝谷」。
主人公トニー滝谷は「習慣としての孤独に馴染んだ人間」。この表現が独特でよい。私もそのタイプかもしれないなと思う。
孤独ではないということは、彼にとっていささか奇妙な状況であった。孤独でなくなったことによって、もう一度孤独になったらどうしようという恐怖につきまとわれることになったからだ。
「トニー滝谷」(文春文庫『レキシントンの幽霊』所収)
映画版は撮影方法(屋外に建てたオープンセットで撮影されたらしい)、坂本龍一の音楽、主演の宮沢りえの存在感によって、独特の雰囲気をもつ美しい作品。かつ原作とは異なるラストで個人的にはかなりお勧め。
興味のある方はぜひ一度ご覧になってください。
50代~60代 「ハナレイ・ベイ」「ドライブ・マイ・カー」
~「こちらでやりくりして、呑み込んで、ただやっていくしかないんです」~

さらにやはり映画経由の「ハナレイ・ベイ」。主人公はサーファーの息子をハワイで亡くした女性。
彼女にわかるのは、何はともあれ自分がこの島を受け入れなくてはならないということだけだった。あの日系の警官が静かな声で示唆したように、私はここにあるものをそのとおり受け入れなくてはならないのだ。公平であれ不公平であれ、資格みたいなものがあるにせよないにせよ、あるがままに。
「ハナレイ・ベイ」(新潮文庫『東京奇譚集』所収)より
「理不尽な死別」という形で「大切なものを突然に奪われた人々」がせめて少しでも折りあいをつけるにはそうやって受容するしかないということか。
そして、短編集『女のいない男たち』も、映画『ドライブ・マイ・カー』に触発されて読んでみようと思った。映画の出来があまりにもよかったから。セリフの一つひとつまで丁寧にきっちりと作りこまれた、じわじわと胸に染みいるような作品だった。
「舞台俳優・家福を苛みつづける亡き妻の記憶。彼女はなぜあの男と関係したのか…」
映画版、原作小説ともに胸にぐっと迫ってきたのが、次のくだり。
そういうのって、病のようなものなんです、家福さん。考えてどうなるものでもありません。(中略)頭で考えても仕方ありません。こちらでやりくりして、呑み込んで、ただやっていくしかないんです。
「ドライブ・マイ・カー」(文春文庫『女のいない男たち』所収)より
「病のようなものなんです」という指摘に救われるような気がした。
このセリフ、小説ではやや唐突な印象もあるかもしれないけれど、映画版ではクライマックスでかなり効果的な使われ方をしており、心を揺さぶられた記憶がある。
たぶん、私自身が人生のすべてにおいて「受容する」という姿勢を受け入れようとしているからかもしれない。ここ何年かは上記のようなセリフに敏感に反応するようになっている。
人生における私には致し方ない事実、不条理とも思えること、傷ついた記憶、不平等、生きていること自体のある種の虚しさや悲しさ。
60代になって老いを意識しつつある私は、なんであれ「受容」する、そうやって生き延びていく、という人生の知恵を欲しているのかもしれない。
そしていま現在 「木野」

同じく『女のいない男たち』所収の作品「木野」では、下記のあたりで思わずうっとなってしまった。私自身、残りの人生を自分なりに楽しめばいいと頭では納得していたはずが、心の奥底ではまだ何かがくすぶっているのか……。
結局のところ、そんな目に遭うようにできていたのだ。もともと何の達成もなく、何の生産もない人生だ。誰かを幸福にすることもできず、むろん自分を幸福にすることもできない。だいたい幸福というのがどういうものなのか、木野にはうまく見定められなくなっていた。
「木野」(文春文庫『女のいない男たち』所収)より
私自身の過去や現在が投影されているかのような文章。この箇所を読むうちになにやら胸が苦しくなり、涙がこみあげてきた。
この作品、やがて不穏な展開が続き、どこに向かうのかわからなくなる。
異様な不安感と緊張感のなか、追い詰められた主人公がついに真実に気づいたときには、私自身、この短編小説のすごさに思わずうならされた。
こんなところに物語を着地させるなんて……。
おれは傷つくべきときに十分に傷つかなかったんだ、と木野は認めた。本物の痛みを感じるべきときに、おれは肝心の感覚を押し殺してしまった。痛切なものを引き受けたくなかったから、真実と正面から向かい合うことを回避し、その結果こうして中身のない虚ろな心を抱き続けることになった。
「木野」(文春文庫『女のいない男たち』所収)より
そう、おれは傷ついている、それもとても深く。木野は自らに向かってそう言った。そして涙を流した。その暗く静かな部屋の中で。
「木野」(文春文庫『女のいない男たち』所収)より
そう、「ドライブ・マイ・カー」にあるように受容して、呑み込んで、ただやっていくしかない。
でも、傷ついたなら、その気持ちを抑え込んでしまうのではなく、その傷や悲しみをきちんと受け止めることも大切なのだろう。
私自身、まだまだ心の奥底に抑えこみ、隠してしまった痛みがあるにちがいない。いつか、すべてきれいさっぱり清算してすがすがしい思いでこの世を去っていけたらと願っている。いや、無理か~(笑)。

最後までお読みいただきありがとうございました!
私自身、ネット上のいろいろな人たちの言葉に日々勇気づけられています。この記事もなんらかの形で少しでも誰かの役に立てばと願っています。
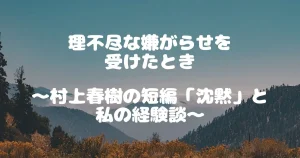
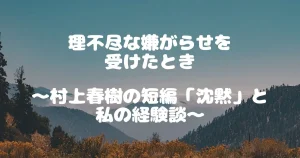




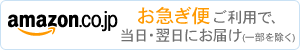





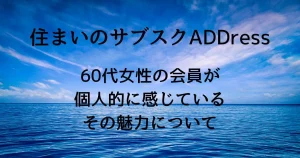
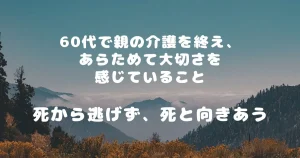
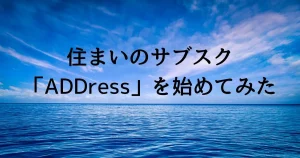
コメント