memento mori(メメント・モリ)という言葉をご存知でしょうか?
メメント‐モリ【(ラテン)memento mori】 の解説
《なんじは死を覚悟せよの意》死の警告。特に、死の象徴としてのしゃれこうべ。人間の欠陥やあやまちを思い出させるものとして、ヨーロッパのルネサンス・バロック期の絵画のモチーフに用いられた。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
中世ヨーロッパの修道院で用いられたラテン語のあいさつだそうです。自分が死すべき存在であることを忘れるな、と。私自身いつどこで覚えたものか記憶にないのですが、久しぶりにこの言葉が頭に浮かびました。
母の死と向きあうなかで感じたことをお伝えできればと思います。
死が怖かった子どものころ、そして突然の父の死

老いや死が怖くない人はおそらくいないでしょう。でも、私は生まれてからずっと祖父母とも一緒に暮らしていたせいか、小さいころから老いや死に怯える気持ちがとりわけ強かったようです。
祖父はいきなり具合が悪くなって入院することがあり、いま思えばたぶん命にかかわるような大病ではなかったのですが、祖父が死んでしまうのではないかと子ども心にも心配していました。
老いて体が弱っていき、いずれ死が訪れる。大好きな祖父との別れがくることを怖がっていたのです。
祖父は晩年脳梗塞で倒れ、手足や言葉が不自由になりました。それでも数年は元気にしていたのですが、やがて寝たきりになり静かにこの世を去りました。母と祖母が献身的に介護していたことを覚えています。
父は私が高校生のとき突然心筋梗塞で倒れ、救急搬送されたもののその日の夜に病院で亡くなりました。
父の死には向きあうどころか、あまりにも突然のことで、茫然自失、あっけにとられるばかりでした。近くの寺で葬儀が行われたのですが、いまだにそこを通りかかるたびに、あのとき訳もわからず制服姿で泣きじゃくっている高校生の自分の姿が目に見えるような気がするのです。
祖母は膀胱がんで入院、手術となりましたが、退院することなく、まもなく亡くなりました。
祖父母の場合は、基本的に母が看病し、世話をしていましたから、孫の私はまだワンクッションあるというか、直接的に介護にかかわって辛い思いをすることはありませんでした。母の手伝いをしていたとはいえ、いわば、はたで見ながら悲しんでいるだけですんだわけです。
そして、私の母のケース。母は脳出血で倒れたのち、体は不自由になったとはいえ12年間それなりに元気でいてくれましたが、最期はあっけなく亡くなりました。急性心筋梗塞。倒れた瞬間に絶命していたのでしょう。
母に限っていえば、長年にわたって一緒に生活し、介護もとことんやり切ったという思いがありました。もちろん後悔や悲しみ、寂しさがないわけではないのですが、心にぽっかり穴があいたような、無力感や虚無感といったものはそれほど強くありませんでした。
しかし、若くして父をいきなり失ったときはかなりつらかったし、あとあとまでその影響は尾を引きました。なにしろ自分の父親がどんな人だったのか、わからないのです。そもそも父とはあまり接触がなかったというか、日中は仕事で不在でしたし、家では無口でおとなしい人だったからです。
30代くらいまでは喪失感や欠落感になんとなくつきまとわれていた気もします。
自分自身、父が亡くなった年齢に達したときは、なんともいえない複雑な思いがしました。とうとう父の年齢に追いつき、追い越していくという不思議な感覚。こんな年齢で逝ってしまったのか、まだまだやりたいこともあっただろうに、と。
最愛のペットとの別れと心残り

そして人間と同列にしてはいけないのかもしれませんが、大切なペットの死。私にとって死と向きあえなかったという後悔が強く残っているのは、数年前、人生で初めて保護した猫を失ったときのことです。
その猫は当初から猫白血病ウイルスに感染していたため、保護して2年後に亡くなりました。獣医さんからもおそらく3年くらいの命だと警告されていたので、覚悟はある程度できていたつもりでしたが、やはり冷静に受けとめられるわけもなく、かなり取り乱してしまいました。
それまでペットといえば犬や小鳥、小動物ばかりで、初めて猫と一緒に暮らしたので、私が猫の習性をよくわかっていなかったのがいけなかったのです。
やせて衰弱した愛猫のせめて世話だけでも焼きたいのに、その子は庭に出たがったり押し入れの奥に隠れたりするばかりで、手を触れようとするとよろよろと逃げてしまうのです。これにはかなりショックを受けました。もう私にはなにもしてやれないのか、せめて私のそばにいてくれたらいいのに……。
そんな愛猫を最後までしっかりと支え、見守ってやるべきでした。自分自身の感情に流されるのではなく、気持ちを強くもって寄り添っているべきでした。
もちろん最後までできる限りの治療や世話をしたのですが、私の弱い心は、死んでゆく愛猫の姿をしっかりと見据え、その子の死を受け入れ、死にゆく命から目をそらさず最後までしっかりと看取ることができなかった。そんな後悔があります。
ともすれば現実から目をそらして、自分だけの悲しみや寂しさに浸っていたように思います。
さいごに

思えば私の人生はよくも悪くも、現実を受け入れる、「受容する」という意識、静かな諦観といったものが欠如していたのでしょうね。現実を捻じ曲げてでも、なんとしても希望を叶えようとする一種のいやらしさや醜さがあったと思います。
もちろんそんなわがままな生き方をしてきたからこそ翻訳家になるという目標もかろうじて叶えられたのかもしれません。「なんとしてでも」というがむしゃらな気持ちが功を奏したのでしょう。
母の介護についてもそうだったのかもしれません、なんとかして昔の母に戻ってもらえたら、少しでも自力で歩けるようになってくれたら。でも結局、そんな願いはむなしく、周囲の誰もがあきらめていたのに、私ひとりが空回りしていただけ。
希望をもち、物事をよい方向へ向けようとする努力や気力、根性もときには必要でしょう。
でもいつも流れに抗って生きるのではなく、老いや病気、死という避けがたいものを真正面からきちんと受け止め、諦観をもって生きていけたらといまさらながら感じています。
いままでこんなふうにわがままにムチャに?生きてこられたのも、ある意味では恵まれていたのかなとも思いますね。とにかく生きる喜びを感じ、当たり前のことを当たり前と思わずに感謝しながら残りの人生を生きていきます。

なんだかとりとめのない文章になりましたが、
最後までお付き合いくださり、ありがとうございました。
なにか少しでもお役に立てば、
どなたかの心に届くものがあれば幸いです



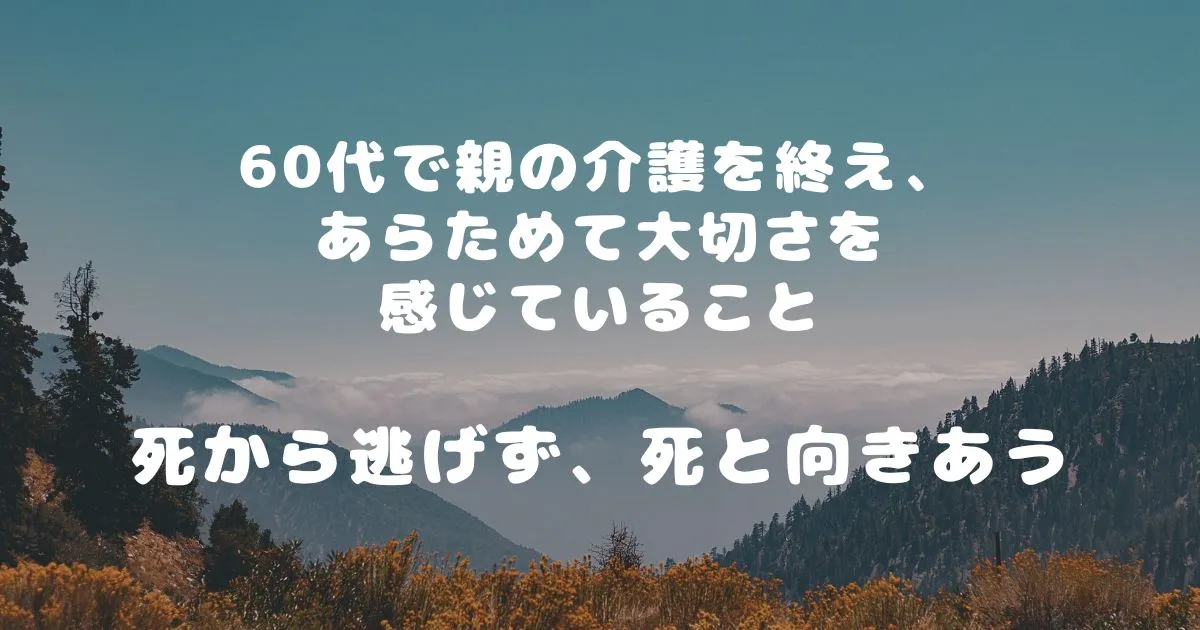






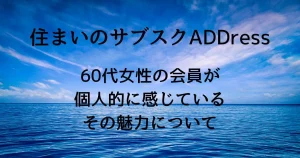
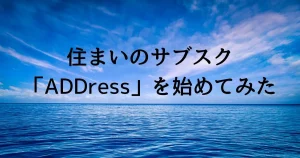

コメント